商売繁盛の御札の正しい祀り方。場所や向き、方角、神棚がない時の対処法
2020年02月26日

こんにちは!茨城県の村松山虚空蔵堂です。
個人事業や法人経営している方にとって大事な商売繁盛。
お寺や神社で商売繁盛の祈祷をしてもらった後は、御札をいただくと思います。
いただいた御札はどのように祀ればよいのだろう?
正しい方角や向きってどっち?
御札は必ず神棚に祀らないといけないのだろうか?
色々と疑問が出てきますよね。
今回は、正しい御札の祀り方について詳しくご紹介します。
商売繁盛の御札の祀り方。置き場所はどこ?
いただいた御札は基本的に神棚へ置きますが、神棚が建物のどこにあるのかが重要になります。
神棚を会社や事務所に設置する場合、明るく清浄で、人が集まり業務の中心となる所に設置するのが良いです。
また、神棚に背を向けて座るのは良くないとされていますが、机の位置などでどうしても背を向けてしまう場合があると思います。その際は以下の点に気をつけましょう。
・神棚を人の目線より上の位置に設置する
・出入口など、神棚の下を通るような場所を避ける
神棚の下を通ることもですが、上を通るのも良くないとされています。
神棚を置く部屋が平屋や最上階でない場合は、神棚の上に「雲」という字の紙を貼ります。
こうすることで「ここが1番上で、この上には何もない」という意味をもたせることができます。
お寺でいただいた御札を神棚に置いて良いのか?と思うかもしれませんが、置いても大丈夫です。
ただし、お寺でいただいた御札と神社でいただいた御札を重ねないように注意しましょう。
商売繁盛の御札の祀る方角について
御札を祀るときは、正しい置き場所だけでなく方角も大切。きちんと調べて祀るようにしましょう。
御札を祀る方角は、東向きか南向きが一般的です。
その理由は、東は太陽が昇る方角、南は日中太陽が輝く方角だからです。
御札の表側を東か南に向けるので、南向きなら北側の壁、東向きなら西側の壁を背に祀ります。
御札を祀るには必ず神棚が必要?
最近は神棚がない建物も増えてきています。
御札をいただいたから神棚を作らなければいけないのか?と思うかもしれませんが、その必要はありません。
以下の点に気をつければ、神棚が無くても御札を祀ることが出来ます。基本的には神棚と同じように場所を選びます。
・立ち上がったときの目線より高く、清浄な場所を選ぶ
・お手洗いや台所、人の出入りが多い入口付近は避ける
・家具の上に置く場合はきれいに掃除して、可能なら白い布などを敷いて清浄な状態を保つ
・御札の見えない場所に両面テープなどをつけて壁に貼るのは可能。ただし画びょうなどで御札に直接穴を開けるのは厳禁
神棚があってもなくても御札はきちんと祀りましょう。
そうすることで、商売繁盛のご利益をしっかり受けることができますよ。
虚空蔵堂の商売繁盛(商売繁昌)祈願について
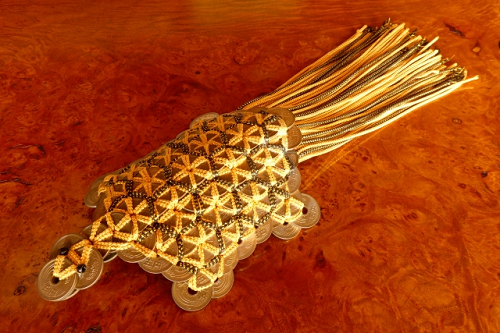
村松山虚空蔵堂の虚空蔵菩薩は、広大無辺な「富」と「知恵」を司る菩薩で、日本では古くから商売繁昌のご利益があると信仰されてきました。
商売繁昌の護摩祈願は通年行っていますので、ご都合の良いときにいつでもお越しください。
祈願料は5,000円、10,000円、20,000円、それ以上の4種類です。
護摩祈願は当日のお申込みとなりご予約はお受けできませんが、団体での護摩祈願をご希望される場合は、事前にお電話かFAXにてご予約を受け付けております。
団体でお越しいただいても皆さまで本堂にお入りいただけますよ。
部署別などでお札が複数枚になる場合は、あらかじめFAXでお申し込みください。
まとめ
・いただいた御札は、基本的には神棚に置きます。神棚を会社や事務所に設置する場合は、明るく清浄で、人が集まり業務の中心となる所にしましょう。また、神棚に背を向けてしまう場合は、神棚を人の目線より上の位置に設置する、神棚の下を通るような場所を避ける、といった点に気をつけます。神棚を置く部屋が平屋や最上階でない場合は、神棚の上に「雲」という字の紙を貼ります。
・お寺でいただいた御札を神棚に置いても問題ないです。お寺でいただいた御札と神社でいただいた御札を祀る際は、重ねないように注意しましょう。
・御札を貼る方角は、東向きか南向きが一般的です。御札の表側を東か南に向けるので、南向きなら北側の壁、東向きなら西側の壁を背に祀ります。
・神棚が無くても御札を祀ることは可能です。その際は神棚と同じように場所を選びましょう。御札は直接貼ることも出来ますが、テープなどを御札の見えない場所につけましょう。ただし画びょうなどで御札に直接穴を開けるのは厳禁です。
村松山虚空蔵堂の商売繁昌護摩祈願は通年行っています。
護摩祈願は当日のお申込みとなりご予約はお受けできかねますが、団体での護摩祈願をご希望される場合は、事前にお電話かFAXにてご予約を受け付けております。
部署別などでお札が複数枚になる場合はあらかじめFAXでお申し込みください。
茨城県の村松山虚空蔵堂は、平安時代に空海(弘法大師)によって創建された寺院です。
茨城では「村松の虚空蔵さん」と呼ばれて親しまれ、十三詣りをはじめ七五三やお宮参り、節分追儺式など様々な年中行事で護摩祈祷を行っています。






